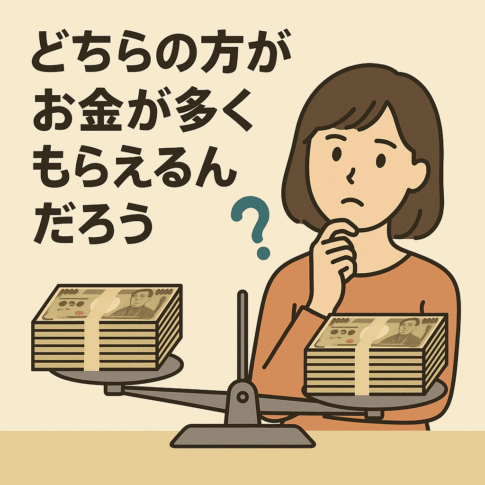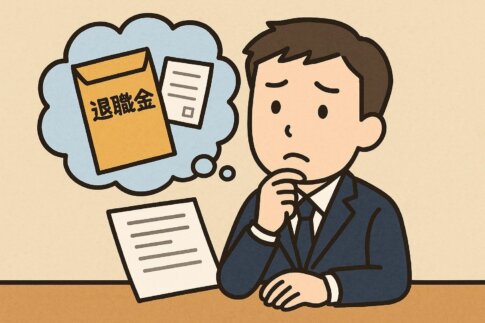「仕事の辞め方がわからない」
「仕事の辞め方の伝え方はある?」
「仕事の辞め方はどういう流れになる?」
仕事を辞めるときは、遅くとも退職希望の1か月前までに上司に伝える必要があります。
ただし、退職の意思表示は口頭ではなく、書面で伝えるのが大切です。
この記事では、仕事の辞め方と基本的な流れ、円満に仕事を辞めるポイント、辞める前に準備しておきたいことを紹介します。
記事を読めば、仕事のスムーズな辞め方がわかり、円満に退社できます。
退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。
条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。
社会保険給付金アシストでは、
長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。
あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。
-
経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート
-
失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内
- その他の給付金やお得な制度もご案内
まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。
相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

仕事の辞め方と基本的な流れ
まずは仕事の辞め方と基本的な流れを紹介します。
あくまでも基本的な仕事の辞め方なので、ご自身が勤務する会社の規則がある場合には、会社の指示に従うようにしてください。
1. 就業規則で退職に関するものを確認する
まずは、就業規則で退職に関するものを確認しましょう。
法律(民法)では、雇用期間が決まっていない場合は、2週間前までに退職を申し出れば退職可能です。
また、雇用期間が決まっているケースでは、やむを得ない事情があるか、契約終了の期限が未定の状態で5年を経過すれば退職できます(参考:民法第626条・第627条・第628条)。
法律とは別に就業規則で退職に関するルールを設けている会社は少なくありません。
一般的な就業規則では、退職の1~3か月前に退職の意思を伝える必要があるとされています。
法律では2週間以内の申告で問題ないとされていても、就業規則に従う必要がある点に注意してください。
2. 退職する意思を上司に伝える
就業規則に規定されている場合には、その期間に従って上司に退職する意思を伝えましょう。
就業規則に規定がない場合には、1か月半前には伝えるのがベストです。
伝え方の詳細は「円満な仕事の辞め方の5つのポイント」で紹介しますが、まずは上司に感謝の気持ちを示しながら、丁重な姿勢で意思を伝えるのが重要です。
3. 退職願と退職届の違いを理解し、提出する
上司から退職の承諾を得られたら、「退職願」または「退職届」を作成し、提出します。
- 退職願:退職を「願い出る」書類。会社に退職を申し出る段階で提出し、まだ撤回できる余地があります。
- 退職届:退職を「届け出る」書類。会社が承諾済み、または一方的に意思を通告する段階で提出します。基本的に撤回はできません。
多くの会社ではまず退職願を提出し、承諾後に退職届を求められるケースが一般的です。
会社の就業規則に従って準備しましょう。
4. 後任に業務の引き継ぎをする
退職が最終的に決まったら、自身が担当している業務を後任に引き継ぎします。
まずは、現在自分が担当している業務を一覧にして、引き継ぎスケジュールを上司や後任者に情報共有をしながら行いましょう。
後任が決まる前から、自分の業務内容を整理しておくことで、引き継ぎ業務を余裕を持って行えます。
5. 仕事関係者に退職の挨拶をする
退職が受理された後には、仕事関係者に退職の挨拶をします。
社外の方には、自身の後任者を紹介し、仕事の引き継ぎにも問題がない旨を伝えておくとよいでしょう。
社内向けの挨拶は、最終出社日に行うのが一般的です。
6. 退職時に返却するもの・受け取るものを確認する
退職時に会社に返却するもの、受け取るものを確認します。
返却するものは、社員証、名刺、パソコン、業務で利用した書類やデータ、健康保険証などです。
受け取るものは、人事から離職票や源泉徴収票などの書類があります。
退職後に失業保険を受給したい場合には、離職票が必要になるので、事前に確認しておきましょう。
円満な仕事の辞め方の5つのポイント
仕事を円満に辞めるための5つのポイントを押さえておきましょう。
ちょっとした気配りで、退職時の印象が大きく変わります。
1. 退職理由はポジティブに伝える
「キャリアアップ」や「新しい挑戦」など、前向きな理由を伝えるのが基本です。
給料や人間関係などネガティブな理由は避けましょう。
2. 繁忙期は避ける
忙しい時期に退職を申し出ると迷惑をかける可能性があります。
区切りの良いタイミングや閑散期を選ぶのが理想です。
3. 引き継ぎ期間を十分に取る
後任がスムーズに業務を引き継げるよう、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。
最後まで誠実な対応を心がけることで好印象を残せます。
4. 転職活動について周囲に話さない
転職先の名前や進捗を社内で話すのは控えましょう。
不要な噂や誤解を避け、静かに準備を進めるのが賢明です。
5. 有給休暇を計画的に消化する
残りの有給休暇はきちんと消化しましょう。
引き継ぎと調整しながら、スムーズに退職日を迎えることが大切です。
退職時の有休消化については、以下の記事で詳しく解説しています。
仕事を辞める前に準備しておきたい4つのこと
退職後は、保険や年金などの手続きを自分で行う必要があります。
ここでは、仕事を辞める前に知っておきたい重要な4つの準備を紹介します。
1. 健康保険証の返還と資格喪失証明書の取得
会社員として働いている間は、会社の社会保険(健康保険)に加入しています。
退職後はその資格を失うため、まずは会社に健康保険証を返却する必要があります。
任意継続を希望する場合でも、一度は会社に返却するのが原則です。
そのうえで、同じ健康保険を継続したい場合は「任意継続被保険者制度」を利用します。
この手続きは退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に申請する必要があり、期限を過ぎると利用できません。
任意継続をすると、保険料は全額自己負担(会社負担分も含む)になりますが、在職中と同じ健康保険組合を使えるため、医療費の自己負担割合は変わりません。
また、資格喪失証明書は国民健康保険に切り替える際に必要な書類です。
扶養家族がいる場合は、家族分も含めて発行してもらいましょう。
退職後は任意継続と国民健康保険、どちらを選ぶべきか迷う方は、こちらの記事で詳しく比較しています。
2. 国民健康保険への加入
会社の社会保険を抜けたら、次は国民健康保険への加入手続きが必要です。
任意継続をしない場合は、退職後14日以内にお住まいの自治体で手続きを行いましょう。
この「14日以内」というのはあくまで目安であり、多少遅れても罰則などはありません。
ただし、手続きが遅れるとその期間もさかのぼって保険料を支払う必要があるため、早めに済ませておくのが安心です。
加入時には、会社から受け取った「資格喪失証明書」を提出します。
また、扶養家族がいる場合は、それぞれが個別に加入手続きをする必要があります。
国民健康保険には、所得が減ったときに保険料を軽減できる『減免制度』があります。
条件や申請手順の詳細はこちらの記事で紹介しています。
3. 国民年金への加入と減額制度の活用
会社を辞めると、厚生年金から国民年金へ切り替える必要があります。
手続きは退職後14日以内に、市区町村役場または年金事務所で行いましょう。
ただし、退職後に収入が減る人も多いため、「国民年金保険料免除・猶予制度」を活用するのがおすすめです。
減額制度を申請すれば、将来の年金受給資格を維持しながら、保険料負担を軽減できます。
4. 失業保険の申請
退職後、一定期間雇用保険に加入していた方は、失業保険(基本手当)を受け取れる可能性があります。
生活を安定させるためにも、早めに申請手続きを行いましょう。
受給条件
- 失業して求職中であること
- 就職する意思と能力があること
- 雇用保険の被保険者期間が一定期間あること
(自己都合退職:2年以内に通算12か月以上/会社都合退職:1年以内に通算6か月以上)
申請の流れ
- 会社から離職票を受け取る
- ハローワークで求職申込みと離職票を提出
- 雇用保険説明会に参加
- 7日間の待機期間を経て、失業状態が確認されると支給開始
詳しい申請の流れや注意点は、以下の記事で解説しています。
給付制限期間の最新情報
2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限期間は「2か月 → 1か月」に短縮されました。
会社都合退職や特定理由離職者(病気・介護・パワハラなど)の場合は、待機期間終了後すぐに受給できます。
失業保険のサポートは専門会社へ相談しよう
失業保険は、退職後の生活を支えてくれる大切な制度です。
ただし、会社都合・自己都合・特定理由離職者などの退職理由によって、受給までの期間や金額が大きく異なります。
制度が複雑で、自分だけで正確に申請するのは意外と難しいものです。
そんなときは、社会保険給付金アシストのような専門サポート会社に相談してみましょう。
アシストでは、提携クリニックと連携しながら一人ひとりの状況に合わせて支援を行っており、自己都合退職でも多く受給できるケースを数多くサポートしています。
また、専門スタッフがハローワークへの申請手順や必要書類の準備を丁寧にフォローしてくれるため、申請ミスや不支給リスクを防ぎ、スムーズに給付を受け取ることが可能です。
退職後の生活を安心してスタートさせたい方は、ぜひ一度相談してみてください。